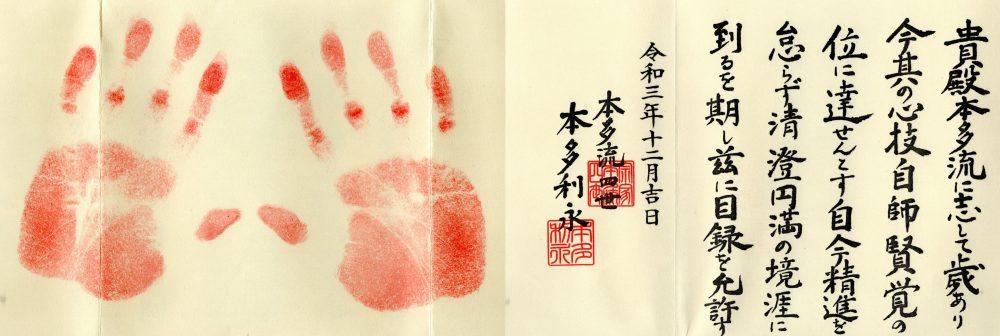弓法とは、五射六科のうち、弓具の取り扱いに関する一連の知識です。
「弓法 弓矢取扱の法なり。射儀の中に籠ると雖も、平生弓矢の取扱に其法を知らざれば美つくさず。」
平瀬光雄『射學要録』より
「弓を扱うことは、射ずしてただ持ち歩くとか、座敷の中にてするとかの場合においては、三指で持つことを法則と致します。三指と申しても、右手の親指、人差指、中指の三指でございます。ゆえにこれより追々お話ししまするが、三指の外にては弓は持つことはありません。
当時世の中の弓術会の催しなどを見ますれば、目的が衛生とか、運動とかにあることなればもっともではありますが、多くは射礼の真似をするにしても丸づかみ、三指でせずして諸手つかみに致しまする。稽古と射礼とでは差はあるにしても、常々その心がけにて致されたいのであります。弓の諸手つかみは真の師を取って習わざる証拠と申して宜しうございます。」
本多利實翁『弓術講義録 弓具之部』より
ここでは当流に伝わる弓具の取り扱い方について、ごく初歩的な、その一端をご紹介します。
【全般】
・他人様の弓具に無断で手を触れぬ事
・弓具を跨がぬ事
・弓具を取り扱う際は周囲の人や器物に当たらぬようにする事
・故障を認めた場合はただちに直す事
・現代では弓矢を持ち歩く際に電車やエスカレータで額木を破損せぬよう気を配る事
・雨天時用の合羽は玄関先で外す事
【弓】
・弓は定期的に乾拭きし表面の汚れを落とすとともに故障がないか点検する事
・弓に足を掛けぬ事
・弓を担いだり、杖のように使ったりせぬ事
・信頼関係の無い者に弓を張らせぬ事
・肩入れは矢束の7割程度とし耳を越さぬ事
・神棚や人に向けて素引きせぬ事
・弽を付けて素引きをするときは弦枕で引かず指で引く事
・弓の張り方、形(成)の直し方、口伝
【矢】
・矢は稽古終了の都度乾拭きし故障が無いか点検するとともに定期的に油で拭く事
・矢を持つ時は板突を隠すように持つ事
・人に向けて矢を番えぬ事
・筈の調整の仕方、口伝
【弽】
・弽は通気性の良い箱や袋に収納し、定期的に陰干しする事
・弽を指したまま弦を張ったり、弓矢以外のものを持ったり、作業したりせぬ事
・弽を指すときは座って指す事
・弽を外したら弽袋の上に置き床や地面に直に置かぬ事
・弽を置く際は弦枕を見せぬようにする事
・弽の指し方、口伝
・押手弽の指し方、口伝
・弦枕の調整の仕方、口伝
【弦】
・弦や中仕掛のほつれは気が付いた都度直す事
・中仕掛の調整を怠らぬ事
・弝の高さ、口伝
過去の『会報』に掲載された記事から、その一部をご紹介します。
「高段者でも道場での作法や弓具取扱に付て無頓着(無知?)な人を散見する。
持的を射手の承諾なくして射込む。道場の習慣? 生弓会本部道場では射手の承諾なき限り射込むな。万一他人の矢を損傷したら賠償義務を負う可きだ。承諾あれば此の限でないとされていた。
一手又は四矢で組を稽古してる場合、落の最後の射が終ってから更に追加して射る。矢取の人が危険だ。
他人の弓を無断で肩入する。承諾を得ても耳迄しか引く可きでないことを知らない。
素引するのに帽子に弦を掛けて引く人が多い。利時先生は「矢を番えてないと捻りの感覚が鈍いので弦が外れて頬を打ち易い。捻りを強くすれば弽を痛めがちである。帽子に掛けずに指で引け」と教えられた。流派的弽の構造の相違もあるかもしれない。
神や人に外竹を向けて素引する人がいる。向けられた人は気持良いものではない。失礼に当る。危険予防の趣旨から行う可きでない。旧軍隊なら物も言はずにビンタを喰はされる―弾は装填してなくても演習でもなくて銃口を向け構えられたら―危険予防のためである。
他人の弽を手に取ってみる。失礼に当る。
巻藁前三米以外の場所で棒矢を番え引込む人がいる。危険予防上絶対にしてはならぬことである。」
『会報』第105号(昭和57年)「生弓会本部道場の思い出」寺澤為太郎 より一部抜粋
【弓】
「現今云う所のアラ弓とは新弓を謂う様です。新弓とは生弓を申します。荒木弓は新古を不問矢のかゝらぬ即ち射込んでないものを云いまして形、力共に順熟して居りませんから其の扱い方によっては狂い易く成弓の初期に当り不安定なものであります。荒木弓の射込み方は新古によって異なります。昔は新弓と云いましても今日の荒木同様に打立藤放しのまゝ三年も枯し村仕上げをしたものです。現代の新弓は一年未満で仕上げたものが多くそれを生弓荒木と云いこれは弓力の直落は勿論の事暑気に於ての射込みは非常に狂い易く従って調子も保てません故に充分の注意を必要とします。生弓の射込みは冬季がよいのです。調子とか冴えとかは別として弓の安定が良く極りますから比較的破損も少く、適当に射込まれた弓は初心者にとって最も適応致します。又現代で申せば三年も枯して仕上た弓は枯れもの荒木と申して斯様な荒弓を射込む時期は三月頃より五、六月頃までがよく其間に於て小村削りして適宜の手巾と力工合を定めます。而して夏季は多く矢数をかけず時々弦を張り素引位いにして十一月頃より本射にかけます。総て荒木弓の射込み中は弦を休めぬ事で弦切れは形力の安定を鈍らし且つ弓も損じますから可成太い弦と矢を用いる事です。次に弓の手入れとしては暑寒とも綿布で拭う事が肝要であります。
兎に角荒弓は矢数五百位射込みますと大体弓の良否に就て見極めがつきますから若し其の間に於て異状を見出した時は早く弓師へ見せる事が必要です。気候とか扱い上から狂いの来た時はその儘にして置きますと直るものも療治相かなわずと云う事になりますから新調弓を扱う場合は特に注意を要します。」
『会報』創刊号(昭和6年)「新弓と荒弓」石津 重貞 より一部抜粋
【矢】
「弓道は一、二月の寒い時はシーズン・オフ等と称したものですが近頃は寒さの中に元気なお弓のお稽古は大変結構な事です。
寒さが続きますと顔や手の肌が荒れます。肌にはクリーム等の油を塗って肌荒れを防いでいます。諸道具も此の寒気と乾燥では表面が荒れてまいります、家の柱も割れを生じます。矢に割れを生じますのも此の季節です。手の肌にクリームを塗る如く諸道具に油を塗ってほしいものです。
矢には胡桃や椿の実を小袋に入れて染み出る油を塗布したものですが近頃は便利なものが出来て廊下や家具の艶出しを用いれば良いのです。
筈は材料に依って竹筈、木筈、角筈、プラスチック等があります、筈は長い間使用していますと筈口が開いてゆるくなり思はぬ失を生ずる事があります、近年は水牛角筈が一番多く使はれていますが此の水牛筈なれば、筈口が大きくなった様な時はよく温ためてヤットコで押さえると筈口は狭くなり一時的に使用出来ます。プラスチックも同様ですが、熱度に依って溶けますから注意して下さい。竹、木、骨筈、は割れ易いですから中関を太くしますと欠ける恐れがあります。
筈の元に巻いてある糸を筈巻糸、羽根の上下に巻いてある糸を上矧糸下矧系と言ます。長く使用していますと糸口が切れて乱れる事があります、此の様な時は糸を巻いて末糸を二、三回位糸の下を潜らせて締め、接着剤を塗って下さい、ホツレを防ぐ事が出来ます。其の上にお手持の塗料があれば塗りますと尚丈夫になります。
羽根は使用中に倒れたり折れたりします。其儘にして使用しますと矢飛に影響します。其の様な羽根を延ばすにはヤカンに湯を沸かし其の湯気に当て湯ノシをすればよいのです。長く湯気に当てゝいますと羽根が浮きますから手早くする事です、手早く羽根を延ばしても羽根と羽中箆に露を生じますから必ず遠火で乾燥する事を忘れてはなりません。乾燥した羽根は生き返った様に美麗になるものです、羽根が浮きましたら、ヘラの先に接着剤を付けて差し込んでください。
羽根には虫が付きますから気をつけねばなりません、羽根を喰う虫は毛織物を喰う虫と同じで体長三、四ミリの小さな毛の生えた毛虫です、虫は埃に付くと言はれますから保存する際には年に二度以上の埃払をする事が肝心です、矢筒や矢箱に除虫剤を取替て入れて下さい。箆に塗る艶出し油が揮発性のものなれば防除の役に立ちます。
矢の根は鏃とも書きますが鏃は征矢の様に戦の矢先の意ですからスポーツの矢には矢の根の表現が良いとされています。矢の根は使っていれば光っているものですが水気がありますと赤錆を生じます、赤錆は恥です、赤錆を生じた時に「砂で磨け」の教えがあります、砂で磨けとは弓を引かなかったから赤錆を生じたのだ、つまり気持がたるんでいるからだ、一生命弓術を練習して垜の砂で矢の根を磨け、と教えたのです、手入の良い矢は黒錆です。
矢のみならず諸道具はお手入をする事に依り愛着心を増し事故を未然に防ぐ事が出来ますし其の品をより以上に尊いものにします、お道具の手入は心を込めて行ないたいもので手入の良い道具は持主の人がらをうかがう事が出来ます、道具の手入は心の手入につながるものがあります。」
『会報』第101号(昭和44年)「矢の手入れ」石津巌雄 より一部抜粋
【弽】
「弓を引く上に於て鞢が如何に重大な関係があるかと云う事は弓道に携る者の日ならずして自覚するものであります。
射形に於て、放れに於て、続いて当りに於て、その強弱に於て、必ずや鞢の良否、適不適は問題となるものです。
鞢は如何なる点が重要であるか。
自己の手に合う事。
流派に適する鞢である可き事。
が第一条件でありましよう。続いて張込の調子、強さ、帽子(親指の処の固い部分)の形、其据付け、人差指と親指との股空の工合等重要な点でありましよう。弦道の付け工合も亦等閑に付されない要点であります。
要するに自己の手にしつくり合つて軽く使い工合の良いと云う事が何よりの事と存じます。
新調の鞢の使用に就ては各先生、各先輩方の教えに従つてなされば間違いはありませんが最初は如何しても手に馴染難い物ですから親指の頭にキチ粉(俗にギリ粉)を少し多分に付けて滑り止めを致します。それから十数本位矢を番へないで素引を致します。其上巻藁に向い、幾分馴染んだ後で的に向う様にすれば結構の事と存じます。
最後に手入法及保存法でありますが、何を申すも濕気は非常に悪い結果を来しますから風通しに当てゝ出来るだけ乾燥させて頂き度いのです。濕気を受ける為めに黴を生ずる事があります。黴の後は腐りが生じ易いものです。特に親指の中の革は汗の為め等で腐り易いものですから常に乾かす事が必要です。」
『会報』創刊号(昭和6年)「鞢に就て」三室共信 より一部抜粋